

雨漏りを根本から解決!
寒い面”に起きる見えない温度差トラブル
屋根の雨漏りが見つけられない
挫折を乗り越えた
今だからこそ
屋根からの雨漏りの専門家
として雨漏りを解決するだけ
ではなく不安を取り除き
「安心して暮らせる」を
提供している
札幌市手稲区の齊藤板金
代表齊藤宏之です
「やもりびと」として活動しています
「家の北側の壁を触るとなんだかいつも湿っぽい」
「北面の天井裏にカビが出やすい」
そんな現象を経験された方は多いと思います
“冷え”ていると湿っているように
感じることもありますが
日射と断熱のアンバランスによる「構造的結露」がほとんどです
北側が“寒くなる”のは当然としても
それだけではないということ
南側は日中に太陽光で暖められますが
北側についてはほとんど日が当たりません
結果として北面の外壁や屋根は
一日中冷たいままで
この冷えた面に室内の暖かく湿った空気が触れると
表面温度が露点を下回り水滴になります
これが「結露」となります
問題は単なる温度差だけではありません
断熱の入り方や通気の取られ方が不均一だと
結露はさらに起こりやすくなります

結露は「断熱の境目」で起きるわけですが
屋根や壁の中では断熱材の切れ目や隙間が
あることで冷気が忍び込むトンネルになり
この冷気の通り道があることで
そこだけ表面温度が下がり湿気が吸着し
やがてカビや染みとなって現れます
とくに北側の屋根裏や物入れでは
外壁との取り合いであったり
天井裏の隅または換気ダクトの周囲に
結露が集中します
物入れなら扉は開けておくことや
壁から隙間を開けて物を置くなどが有効です
こうなると断熱を厚くすれば
結露が起こらないように感じますが
ここはそう単純ではありません
内部の湿気が抜けにくくなるからです
昔の家は風がスースー入ってくる
隙間が多かったために
重大な結露が起こりにくかったのですが
今の家(最新の住宅を除き)は換気が不足すると
結露が起こりやすくなります
そのため屋根自体に通気層を設けることや
壁との空気の流れをつなげることなど
バランスが大切といえます
DIYでできる北面チェックとして
外壁や屋根の苔がわかりやすくなります

湿気が滞留しているサインで
表面が乾きにくくなっていますのでこの面は注意です
窓枠まわりのゴムの黒カビは
いつも結露が起きている証拠となります
空気の流れが滞っている証拠でもあり
換気や断熱の見直しをするのが理想です
結露を“止める”のではなく
“乾かす”方向へ持っていくことがベストです
もちろん起こらないことが
一番ではあるものの
湿気が発生しても逃げられる構造であれば
問題になりません
そういう我が家においても窓は結露しますし
北面のクローゼットの中はカビやすくなります
対策としては結露を吸い取るものや
こまめな換気また扉を開けておくなど
生活の中でできる対策もありますので
まずは意識して対策してみることをおすすめいたします
関連記事
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別記事
- 2026年1月 (28)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (31)
- 2024年12月 (31)
- 2024年11月 (30)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (30)
- 2024年8月 (31)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (30)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (29)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (30)
- 2023年10月 (31)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (31)
- 2023年7月 (31)
- 2023年6月 (30)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (30)
- 2023年3月 (31)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (30)
- 2022年10月 (31)
- 2022年9月 (30)
- 2022年8月 (31)
- 2022年7月 (30)
- 2022年6月 (30)
- 2022年5月 (31)
- 2022年4月 (30)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (28)
- 2022年1月 (31)
- 2021年12月 (9)





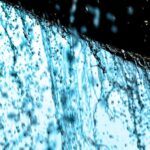










Profile
屋根の雨漏りが見つけられない挫折を乗り越えた今だからこそ、屋根からの雨漏りの専門家として雨漏りを解決するだけではなく不安を取り除き「安心して暮らせる」を提供している
札幌市手稲区の「齊藤板金」代表の齊藤宏之です